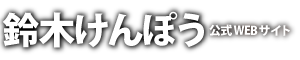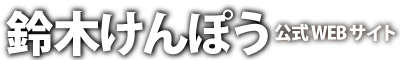渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。お越しくださいましてありがとうございます。
夏休みですね。小学生の保護者の皆さんはこどもの対応にご苦労なさっているかもしれません。
特に共働きのご家庭はたいへん。共働き家庭の強い味方、それが放課後クラブです。学童保育を運営している他区と比べ弾力的に多くのこどもに対応できるため「学童待機」が存在しない! その代わりに若干対応が手薄になってしまう放課後クラブ。本日は夏の対応についてご意見を伺います。
<記事サマリー>
- もともと放課後クラブは「長期休みはお弁当を持ってくることが利用条件」であり、「親の愛情」という観点から手作り弁当が必須であった
- 給食の提供は「食数が安定しない」注文弁当の利用は「アレルギーや職員体制、設備などの観点」で不可とされていた
- 平成27年~28年に答弁が一部変更され、「食事作りプログラムで保護者の負担軽減」「コンビニ等の購入した弁当OK」「給食以外の昼食の提供は保護者の要望を受けて研究する」とされる
- それから4年たち、再度検討すべき時かもしれない
<本文>
長期休みにおける放課後クラブの昼食対応については長らく議論されています。10年前くらいは区長・教育委員会や自民党さんを中心に「お弁当は親の愛情」という考えが根強くありました。
平成26~28年に議論がおおいに進みます。以下、質問(提案)→答弁、です。
- 平成26年3月堀切議員:仕出し弁当利用は→お弁当持参が利用の条件なので考えていない
- 平成27年3月堀切議員:注文式のお弁当を→お弁当を通じて親子の絆
- 平成27年6月鈴木けんぽう:仕出し弁当を提供しては→アレルギー対応など安全配慮をはじめとする様々な課題がある
- 平成27年9月近藤議員・堀切議員:給食を提供しては→日々の職数の増減が激しいので難しい
確かに、夏場の食中毒の恐ろしさ、それ防ぐための保管の場所や対応する人で、そして人数の増減の多さなどを考えるとなかなか一歩を踏み出せない、というのも正直理解できるのです。
いい加減に運営して事故があったら最悪ですし、また受け入れ体制が整ってもアレルギーなど面倒でかつ増減の多いこどもたちのお弁当を事業者が安定して供給してくれるのか…というのは当時も今も非常に不安な要素です。
保育園や学童保育と違い、登録した全児童が使える放課後クラブでは利用者数は日によってかなり増減がありますから、対応が相当難しいのは間違いありません。
ここで、平成27年11月議会で転換がはかられます。4月に長谷部区長が就任してようやく前体制の方針から抜けたということでしょうか。
- 平成27年11月鈴木けんぽう:昼食の提供を → 昼食づくりなどのプログラム充実で保護者の負担軽減につなげる/給食以外での昼食の提供はアレルギー事故等の課題はあるが保護者の要望を受けて研究を進める
保護者の要望をもとに研究する、というスタンスですね。さらに平成28年度あたりからコンビニ等の購入した弁当も利用可能になり(それまでは弁当箱にうつして持ってこさせていた)、いったん議論が収束しました。
現在は放課後クラブをめぐる議論は
- 利用スペースの狭さ
- 適正な運営体制(スタッフ数など)
- 充実したプログラム
に移っています。
議論が収束した平成27年から4年。放課後クラブの長期休みの昼食については、次年度に向けて改めて本格的に議論を始めるべきなのかもしれませんね。
そのためには「保護者の声が必要」です。こちらのフォームからみなさんの声をお聞かせください。

- 投稿タグ
- 教育