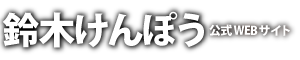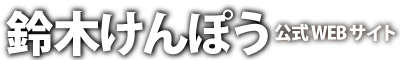渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。
選挙でたくさん演説していると、それがそのまま自分の考えや今までの提案を整理することにもなっています。
たとえば、タブレットを使った教育。渋谷で全児童生徒に配布されて2年目となっています。街頭で話していて、「理想のタブレット活用」が改めて明確になりました。

もちろんいろんなアイディアがあるのだけど、おさえておきたい条件として
- 先生が安定して実行できる。トラブルは困る
- 準備にそれほど時間はかけられない。交渉・調整などが発生するようなことは日常使いには向かない。むしろ先生の負担軽減のほうが望ましい
- 当然のことだけど教育効果が見込まれること。たのしかったねー、でもなにやったんだっけ? では無意味です
- 権利やら個人情報流出防止やらを考えておく
この辺をきちんと押さえておかなければ実務的に無理が出てきます。そうすると、興味深い事例なんて全先生・生徒でできるわけないので(能力的にも準備にかけられる時間的にも)、
- 日常的に使い倒すこと→操作への習熟
- 授業での活用事例をテンプレ化し共有すること→教員負担の軽減、学習効果の向上
- 学習記録を残して指導、評価に反映させること→学習効果の向上
- 画面拡大や読み上げ等の活用→学習障害など個別事情への対応
- 連絡やコミュニケーションを確実にする(大人は気軽なコミュニケーションはメッセージアプリで、証拠を残したいときはメールで、なんて使い分けてませんか? こどもたち同士の様々なコミュニケーションを活性化させたいし、小学校では連絡帳をタブレットで代替させたい!)
このあたり、地味で確実な活用を進めるのが私の使命だな、と思っています。
・・・ほんと地味ですねー。でも、派手だけど中身スカスカの提案なんて害しかありません。着実な改善を進めたいです。
最近よく「近頃の大学生はパソコンも使えない…」みたいな話を聞きますが、ICT機器への習熟は家庭環境、場合によっては収入などの事情も大きいです。すべてのこどもにタブレットを配布することは、家庭環境によらず習熟できる基盤としてとても重要です。
またトラブルを避けるためには、素直に聞いてくれる・恥ずかしがって隠そうとする前の年代からおとながサポートしながら使う体験を重ねていくことが大事です。ですから、低学年から発達段階に応じてタブレットを使うことはその意味でも貴重な取り組みです。
ぜひ、大事に育てたいです。タブレットの活用。
- 投稿タグ
- 教育政策