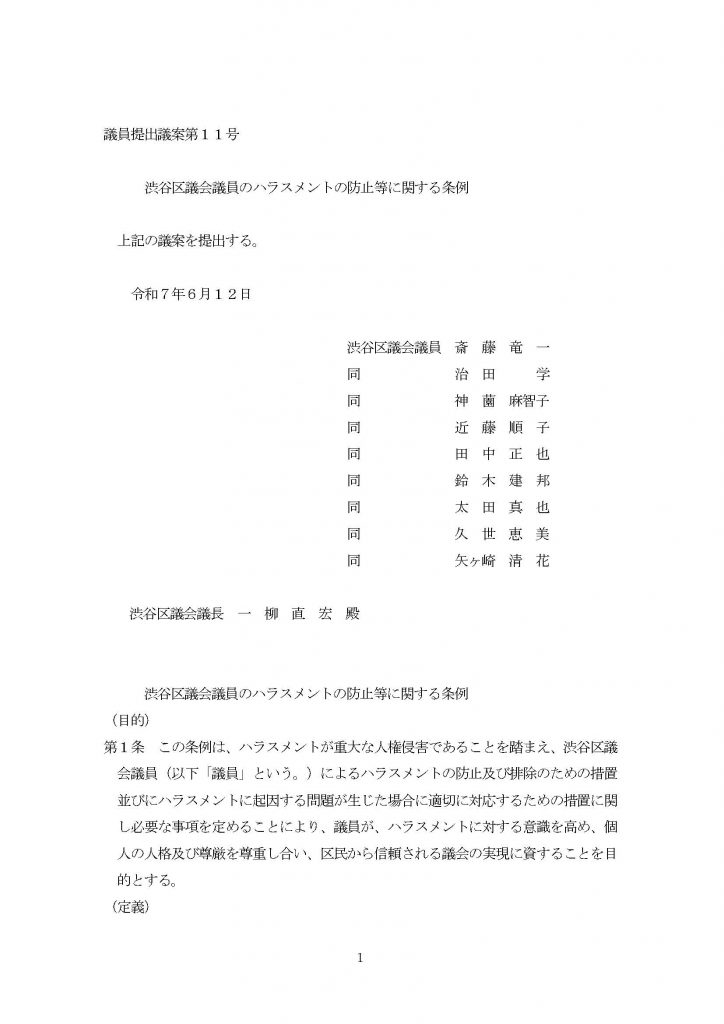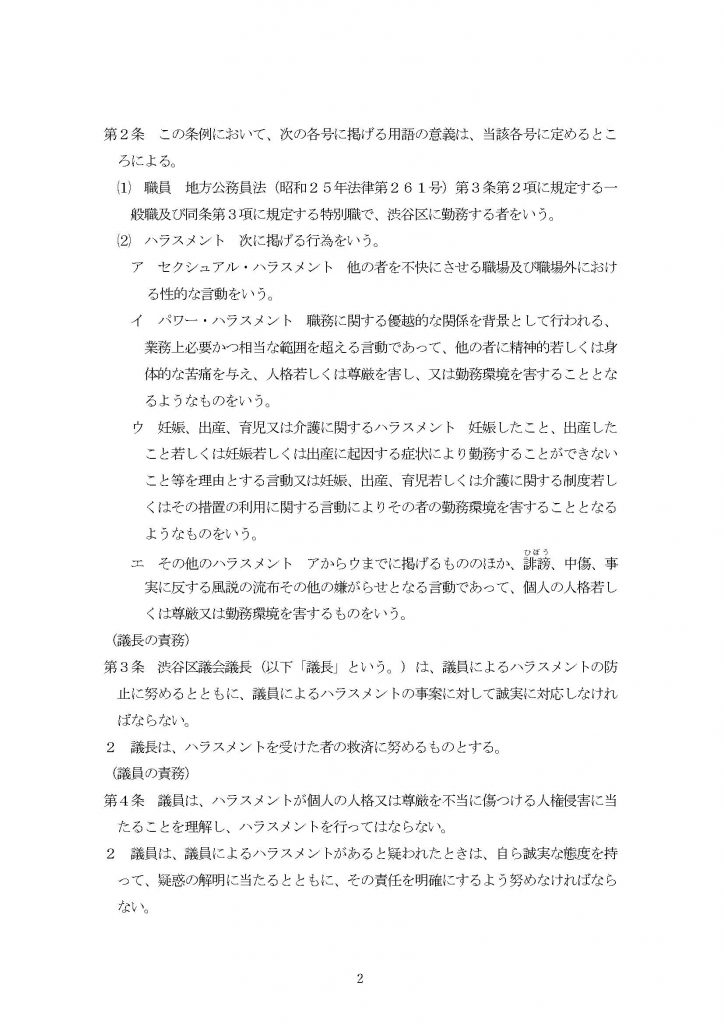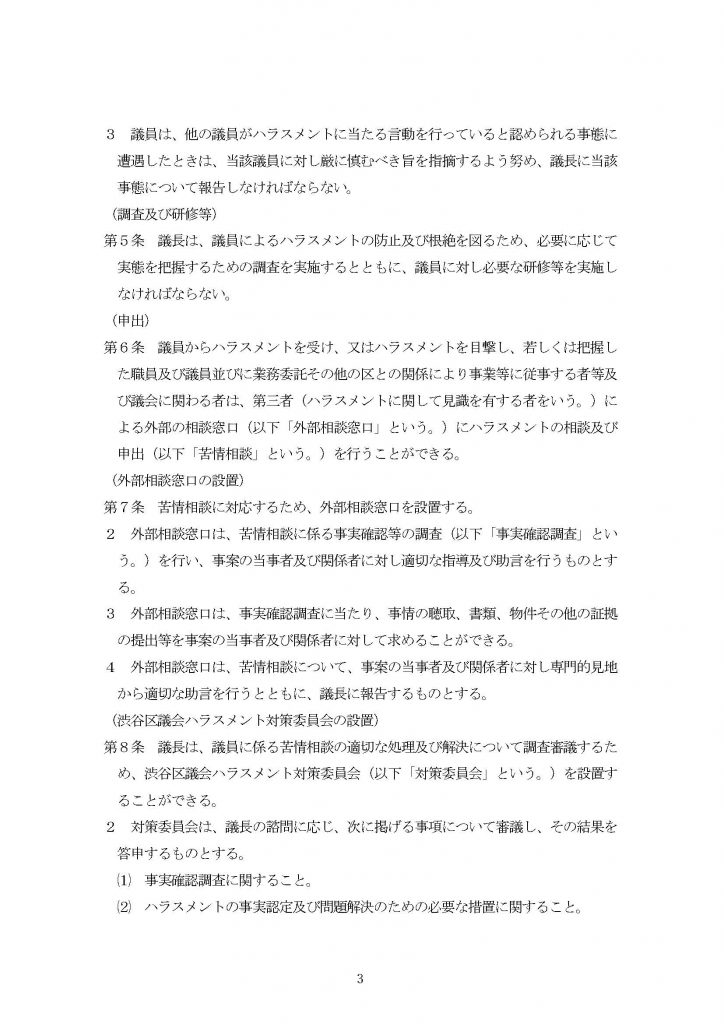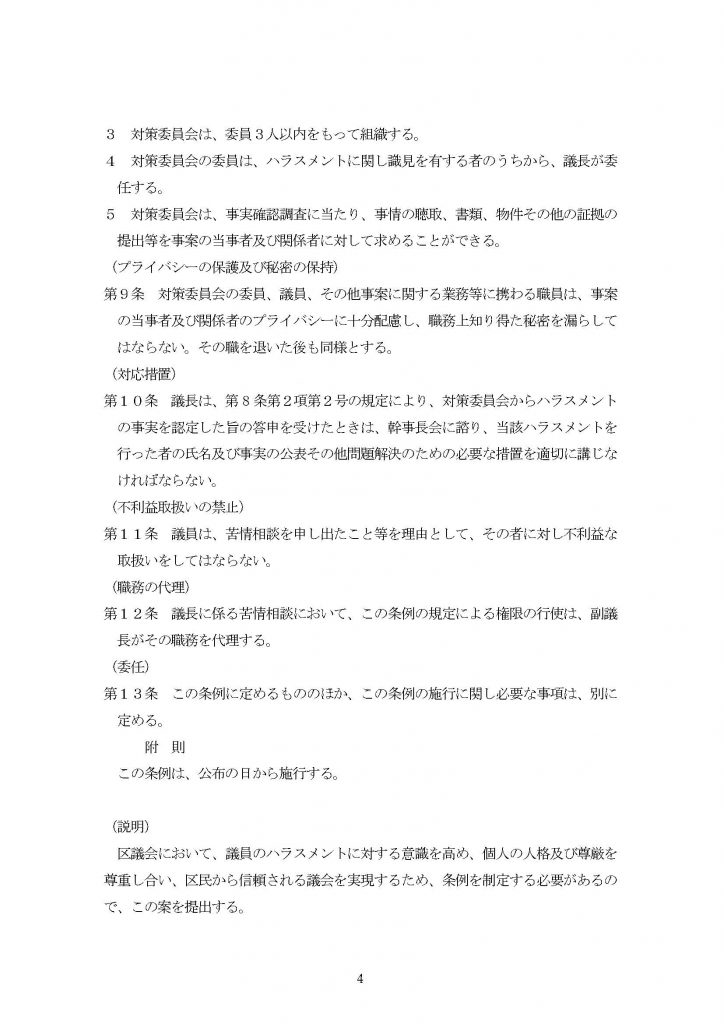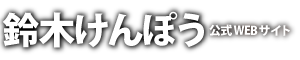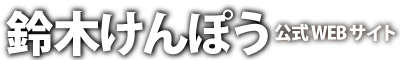渋谷区議会で「議員によるハラスメント防止条例」が施行されました。
この条例の目的は、議員による不適切な言動を防ぎ、被害があったときにはきちんと対応する仕組みを整えること。
とくに重要なのが、「誰が、どんなときに、どこに通報できるか」、そして「通報された議員はどうなるのか」という点です。
この辺、解説していきます。議員のハラスメントを「みたりきいたり」した方もご参考にどうぞ!
目次
■ なぜこの条例が必要だったのか?
2025年2月、「渋谷区職員等のハラスメントの防止等に関する条例」が制定され、区職員や業務委託先などによるハラスメント対策が一貫性を持って動き出しました。
議会では以前から議員による職員への暴言や軽いセクハラ、圧力的な言動が噂される場面がたびたびありました。
令和6年9月には、Facebookや選挙公報で職員に関する事実と異なる情報を拡散したことにより、堀切議員に対する問責決議が可決されました(参考リンク)。
こうした背景のもと、「区職員に厳しくルールを求める以上、議員自身も襟を正さなければならない」という意識が高まり、今回の議員によるハラスメント防止条例が成立しました。
目的は明確です。議会が信頼される存在であり続けるために、ハラスメントを防ぎ、起きた場合にきちんと対応する制度をつくることです。
■ 通報・相談できるのは誰?
以下のような、渋谷区議会と関わる立場の方すべてが対象です:
- 渋谷区職員(正規・非正規含む)
- 区議会議員
- 区から業務委託を受けている事業者やその従業員
- その他、議会に関わる関係者(取材・傍聴・来庁者など)
つまり、「議員と接点のある人すべて」が通報・相談できます。(6条)
■ どんなときに通報・相談できる?
相談できるのは、次のようなハラスメントに該当する言動です:
- セクハラ(不快な性的言動)
- パワハラ(地位を利用した精神的・身体的な圧力)
- 妊娠・出産・育児・介護に関する差別的発言や扱い
- 誹謗中傷、根拠のない噂の流布など人格攻撃
自分が被害にあった場合だけでなく、「目撃した」「人づてに聞いた」という場合でも相談が可能です。(6条)
■ 相談先はどこ?
条例では、外部の第三者機関による相談窓口の設置が義務づけられています。
- 区議会とは独立した立場の専門家が対応
- 実態調査や当事者へのヒアリングも実施
- 必要に応じて議長へ報告し、後の対応につなげる
なお、「通報したことで不利益な取り扱いはされない」と、明確に保護規定が定められています。(11条)
■ 通報された議員はどうなる?
通報は次の流れで対応されます:
- 外部相談窓口が事実関係を調査(7条)
- 必要に応じて「渋谷区議会ハラスメント対策委員会」が設置され、調査・審議が行われる(8条)
- 委員会が「ハラスメントの事実あり」と認定した場合は、議長が幹事長会に諮って対応を決定(10条)
対応はたとえば、
- 氏名とハラスメント概要の公表
- 関係者への謝罪勧告
- 議会内での指導・再発防止措置
など、実態に応じた問題解決のための措置が取られます(明文化されているのは公表のみ)。
「身内でうやむやにせず、第三者の助けを借りて制度的にしっかり対応する」という強い姿勢で行います。
■ まとめ:議員にも明確な責任と対応を制度化
この条例により、議員によるハラスメントに対して「声を上げられる」「制度として対応される」「再発防止につながる」流れが明文化されました。
区議会で人権と尊厳が守られるルールを整えたことは大きな一歩です。
次のブログでは、実際の「外部相談窓口」の活用方法や、相談の流れをもう少し詳しくご紹介します。
「困ったときに、どこへ、どう伝えればいいのか」。その具体的な手順も知っておくと安心ですね!
(私も対象なので、通報されないよう気をつけます 笑)
(参考)条例
議案として議会に提出されたものです