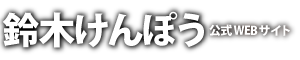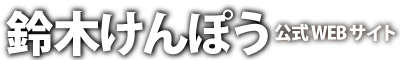渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。
参議院議員選挙が終わりましたね。当選された皆さんおめでとうございます。惜しくも涙をのんだ候補者の皆さん、めげずに頑張ってください!
また関係者の皆さん、本当にお疲れさまでした。
私も今回は、どこに投票するか随分悩みました。有権者の皆さんもお疲れさまでした。
さて、今回の選挙について、無所属地方議員の立場から少しだけ感じたことを書き残しておこうと思います。
(なお、これは結果が出る前に書いていますので、内容と多少のずれがあるかもしれません。その点はどうぞご容赦ください。)
<与党>
まず、自民・公明の与党については、議席を大きく減らす結果となりました。
今回の選挙では、「物価高への対応」や「税・社会保険料の負担軽減」、そして「外国人対応」の2点が、大きな論点でした。
物価高の背景には、円安や人手不足によるコストプッシュ型インフレがありますが、これは結局、大胆な金融緩和を伴ったアベノミクスの負の側面が表れたものとも言えると思います。
また外国人政策についても、アベノミクスによるインバウンドの急増(約3倍)や外国人労働者の増加(約2倍)が、地域との摩擦を生んでいる側面もあるでしょう。
つまり、アベノミクスの「負の遺産」が、コロナ禍を経て噴き出した――そんな構図が今回の選挙の背景にあったのではないかと私は見ています。
もちろん、アベノミクスは大きな成功も収めたと評価できると思います。長く続いたデフレからの脱却、株高や企業業績の回復といった果実をもたらしました。当時は企業や資産を持つ方々がその恩恵を受け、与党の支持率も安定していました。
ただ、「トリクルダウン」が最終的に国民全体に十分行き渡らなかったことが、今日の停滞や不満を生んだようにも感じます。構造改革や新産業の創出が不十分で、賃金は物価に追いつかず、少子高齢化も止められないまま。エネルギーコストやオーバーツーリズムも大きな課題です。
「果実は先に、負担は後に」という構造であり、今回はそのツケがまわってきた――そう考えることができるのではないでしょうか。
<参政党>
今回、ひときわ注目を集めたのが参政党でした。
私の身近にいる矢野議員は、本当に誠実で、一生懸命真面目に取り組む方です。そうした空気が党の中にあって多くの方に支持されたのだと思います。
一方で、陰謀論めいた話や差別的な発言なども見受けられ、気になる点があるのも事実です。今後国政で本格的に活動していく中で、そうした部分が改善されていくことを強く願っています。
人は「信じたいものを信じる」傾向があります。それを乗り越えていくには、科学的根拠や客観的な検証が不可欠です。根拠のない思い込みは、時に社会をゆがめてしまうことがありますから、批判の声にも耳を傾け、主張や政策を妥当なものへと磨いていっていただきたい。
この数十年、多くの新党が生まれては消えていきました。その多くで足を引っ張ったのが、「不適格な人材」と「内部対立」でした。勢いが出ると、いろんな人が寄ってきます。中にはとんでもないトラブルを起こす人もいる。そのたびに、政党への信頼が失われ、支持が落ちていくのです。
この「選別」をどれだけ適切にできるか――それが、参政党が今後どうなっていくかの鍵になると思います。
<国民民主党>
都議選の直前までは、非常に強い追い風が吹いていました。ですが、山尾志桜里さんの公認問題をきっかけに、一気に流れが止まってしまいました。もしあの件がなければ、国民民主党のブームが続き、参政党の台頭もここまでにはならなかったかもしれません。
政党の最も大事な機能は「公認の判断」と「政策の集約」です。今回は公認の判断面で苦い失敗をしてしまいました。
気になるのは、党内に健全な批判勢力が見当たらないことです。違う見方から冷静に物事を検討できる人がいれば、別の判断が導き出せた可能性もあったのではないでしょうか。
とはいえ、選挙期間中の盛り上がりはかなりのもので、数字的には十分躍進しました。ここからは、地道に、そして誠実に信頼を積み重ねていってほしい。心からそう願っています。
<チームみらい>
今回の選挙で新たに注目を集めたのが「チームみらい」でした。安野さんの語りかけはまっすぐで、対立をしないことを主眼にしつつ政策立案にスピード感や一体感があり、多くの方の心に響いたと思います。
一方で、私自身が受けた印象は、やや「理想が先行している」というものでした。既存の政党が、現実の壁や制度の限界の中で試行錯誤している部分を飛び越えて、「こうすればいい」と提示している。いわば「ぼくの考える最強の政策」という感じで、現実の複雑怪奇さを反映できていないと思います。
たとえば「資産に基づいた支援を自動的に行う」という政策を取り上げてみましょう。
実際に実現するには、
- 国が個人の資産情報をどこまで把握していいのか
- 支援を受けたくない人をどう扱うのか(少数でも一定数います。筋金入りの無政府主義者なのだろうか)
といった微妙な価値判断が避けられません。その意味で、そんなに軽く言えるはずないのにな、と思ってしまいます。
理想と現実の調整――これは政治の本質的な仕事でもあります。だからこそ、チームみらいが国政で1議席を得て、現実の複雑さに直面したとき、どんな判断をし、どう折り合いをつけてグレードアップしていくのか。先行きを期待してみたいと思っています。
長くなってしまいましたが、今回はここまで。
政治は難しい。でも、私たちの暮らしに直結する、とても身近なものです。だからこそ、時には悩みながら、関心を持ち続けていただきたいですね。
あなたが選んだ政党・政治家が、どんな風に社会を変えていくのか。ぜひ見守ってください。
それでは、また。