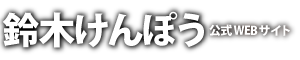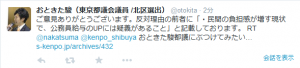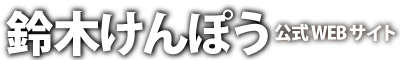渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。
最近、ブログ書くのが楽しいです。いろいろ試してみています。
さて、ブログ書きの大先輩(って言っても、議員としてははるかに後輩なんだけど)のおときた駿都議会議員が、都議会議員のボーナスのありかたに関連してちょっとおかしな投稿をしていたので、疑問点を書いてみます。
ちなみに、私も今回議員報酬・期末手当の値上げに反対しています。方向性は同じなんですけどね…
いろいろ疑問はあるんだけど、たった一つだけ問うならば、
「なぜ、都議会議員のボーナスをあげないために、都庁職員の給与条例に反対したの?」
です。
まるで、「江戸の敵を長崎で討つ」みたいで、ずれてませんか?
おかしいですよね・・・
<おときた駿議員のブログに書いてあること>
それでは、おときた駿議員のブログを見てみましょう。
アベノミクス効果によって(?)民間の所得水準は向上したとされ、
今回は数年ぶりに東京都職員の給与がUPする条例案が提出されました。
この「民間の所得水準」の算出方法自体、倒産した企業を含めていないなど
非常に疑義の多いものでして、消費税の増税などで都民の皆さまに負担をお願いする一方、
公務員給与が上がるというのは納得しがたい部分があります。
そしてこの給与の改正に伴い、
期末手当(ボーナス)も0.25ヶ月の上乗せで1.8ヶ月分になったんですけど、
なぜか都議会議員のボーナスも一緒に連動して増えるという…。
都議会議員の法律的な位置づけは「特別公務員」にあたり、
その議員報酬は別の条例で定められています。
しかしそちらの条例の中で、
「期末手当については、職員の特別職の規定に準ずる」
となっておりまして、棚ボタ的に期末手当が上がってしまうというカラクリです。
なるほど。
「議員にボーナスが必要か」「ボーナスの査定の方法は適正か」というのは重要な論点であり、東京都の指定職に連動して決めるというのは一つの方法でしかありませんから、それに対して否定的にとらえるのは理解できます。
東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第六条第二項をみますと、ちょっと難しいですが、確かに東京都の指定職を基準とするとなっています。
「カラクリ」とか書いてあるけど、要は都庁の指定職のボーナスが下がれば下がり、上がれば上がる、というシステムにしているにすぎませんね。おときた駿議員独特の書き方、というか煽り方なんでしょう。
問題はそのあと。
12月1日に職員の給与改定を行うという手続き上、
この条例案については議会初日の11月28日に中途議決が行われましたが、
・民間の負担感が増す現状で、公務員給与のUPには疑義があること
・期末手当の増額に、都議会議員が連動するのは制度上不備があること
を主な理由として、「かがやけTokyo」都議4名は条例案に反対を致しました。
が、その他120名余の都議会議員は全員賛成で、原案可決となっています。
同時期に行われていた衆院選挙では「身を切る改革」を
主張している政党もあったのですが、どうしたのでしょうか…?
ドサクサにまぎれて都議会議員のボーナスが上がったので、支給額が250万を突破しました
反対理由がいくつかある中で、特に2つの反対理由を示しています。
1つ目は、ストレートなので意味が分かります。じゃあどの水準が適正なのか、どのような決め方が妥当なのかを示す必要はあると思いますが、反対理由としては「そういう意見もあるだろうな」と感じます。
しかし、2つ目はよくわかりません。都議会議員の期末手当が連動している、という制度が不備だから「職員の給与条例」に反対???
「都職員のボーナスあげちゃうと議員のボーナスが上がっちゃうから、都職員のボーナスもあげちゃダメ」
ってことですよ、かんたんに言えば。
この論理を使ってしまうと、都職員のボーナスを増額することはどんな場合であっても不可能になります。いや、減額するのも困難(おそらく、下げるときは制度上の不備があってもそれはいいことにするんだろうけど、それはちょっと整合性とれてませんね)になるでしょう。
本来であれば、都職員のボーナスについては、その水準の是非、手続きの是非、で賛否を決めるべきです。
その上で、「都職員のボーナスと連動して都議会議員のボーナスが連動する」ことについては、その制度を規定している「都議会議員の報酬条例」の改正をめざすのが筋です。江戸(都議会議員の報酬条例)のかたきを長崎(都職員の給与条例)でとるのは無理があります。
都議会議員なんだから、都議会議員の報酬条例について改正案も出そうと思えば出せる(これは強硬的な手段)し、問題点を指摘して他党や都知事に制度改正を呼びかけることもできる(これは柔軟な手段)わけです。職員の条例とは切り離すのが本来のやりかたでしょう。
ということで、給与条例についてはストレートに「民間の負担感が増す現状で、公務員給与のUPには疑義があること」だけを反対理由にしておいた方がよかったんじゃないかな、都議会議員のボーナスと連動していることを制度上の不備として反対理由にするのはかなり無理筋だな、と思います。
ただ、討論原稿自体をじっくり読んでいるわけではないので、もしかしたらこの辺にも触れて説明があるのかもしれません。それでも、一般に向けてブログに書くなら慎重にすべきでは。
<反対を主張する時こそ、丁寧な論理が必要>
なぜこういうことを書くかというと、議員は過去に言った主張・議案討論で自縄自縛に陥ることが結構多いからです。
よく「ブーメラン」なんて言われますね。あれもそうです。過去の発言に縛られます。
議員は発言の整合性が問われます。「賛成はできないけど、彼の言っていることはそれなりに筋が通っている」と思われないと、いずれブーメランでやられます。
特に、反対する時は相当慎重にやらなくてはなりません。役所の提案に賛成する時は楽なもんです。「役所の言うとおりだ」って言えばいいだけだから。反対の主張をする時はかなり綿密に論理を組み立てていかないと、後々ブーメランや落とし穴が待っています。
先ほども書いたように、「他の条例(今回は議員の報酬条例)に不備があるから反対」とすると、その不備が解消されない限り職員のボーナスをいじる条例改正には全て反対しなくてはならなくなります。都議会の事情によって都職員の期末手当が変更できないというのはおかしな話。そのおかしな話をずーっと強弁しなくちゃならなくなる。
そうすると、足元を見られるようになる。「威勢のいいこと言っていても、おかしなこと言っているじゃないか」って。筋道立てて主張していかないと、空回りするばかりで社会なんて変えられないんです。
少なくとも別な条例の不備を理由にするようなのはかなり問題だなぁと…
ということで、おときた駿都議は発信力もあるのですから、ミスだったのなら速やかに修正していただいて、正道を歩んで行っていただければなぁと願ってやみません。
ということで、触発されたのでのちほど渋谷区議会議員のボーナス、給料なども投稿したいと思います。
ではではー。
※今回は、おときた駿都議をリスペクトして、ちょっとタイトルや画像を工夫してみました(笑)
(追記)14時4分
おときた駿都議のツイッターでこのような返答をいただきました。
AとBの二つの理由があって、BがダメでもAがのこるからいいじゃん、ということでしょうか。そういうこと言ってるんじゃないんだけどな。
なんの発展も深化もない、論理的にも疑問が残る残念なコメントでした。まぁ、お忙しいところコメントいただいただけ感謝すべきかなと。
(追記2)21時
ちょっとわかりにくいところがあるのかな、と思い、焦点を絞りました。
もとの文章も取ってあるので、もし読みたかったらご連絡ください。
- 投稿タグ
- 渋谷区議会改革, 渋谷区議会議員の給料・期末手当